ゴールデンウィークが終わると、
ゴールデンウィーク後には、以下のような代表的なイベントがあります。
5月中は、
・母の日(5月の第2日曜日): 日頃の感謝を込めて母親にプレゼントを贈る日です。
・八十八夜(5月2日頃): 立春から数えて88日目の日で、新茶の季節の目安とされています。
・潮干狩り(地域による): 5月は潮干狩りのシーズンを迎える地域が多くあります。
・各地の春祭り: ゴールデンウィーク後も、地域によっては春祭りが開催されます。
6月になると
・父の日(6月の第3日曜日): 父親に感謝の気持ちを伝える日です。
・梅雨: 6月は多くの地域で梅雨入りし、雨の日が多くなりますが、紫陽花(あじさい)が見頃を迎えます。
・衣替え: 6月1日は多くの学校や企業で夏の制服や装いに変わる衣替えの日。
6月も中旬頃になれば、「お中元」の準備が始まる、という初夏のスケジュール感。
お中元の時期は、日本各地で贈る時期が異なることが知られています。
日本各地でのお中元の時期

お中元を贈る時期を地方ごとに、大まかにまとめると
- 関東・東北: 7月1日~7月15日
- 北海道: 7月15日~8月15日
- 東海: 7月15日~8月15日
- 関西: 7月15日~8月15日
- 中国: 7月15日~8月15日
- 四国: 7月15日~8月15日
- 九州: 8月1日~8月15日
- 沖縄: 旧暦7月13日~7月15日
沖縄は「旧暦」を基準とすることから、年によって変動します。2025年は8月7日~8月9日頃ということになりますね。
贈る時期から、お中元の準備開始の時期を考えれば、贈る時期の半月~ひと月ほど前あたりから、準備を始めるのが一般的。
準備開始の目安:
- 関東・東北地方: 6月中旬頃から
- 北海道・東海・関西・中国・四国地方: 6月下旬頃から
- 九州地方: 7月上旬頃から
関東から北の地方では、6月半ばごろから、もうお中元の準備が始まるということになります。
日本全国、6月中旬から7月上旬には大半の方が、お中元の準備を始めます。
最近では、早めにお中元の準備を行う傾向もあって、インターネット・オンラインストアなどでは、6月頃からお中元の受付を開始しているのを見かけます。
早めに準備することの最大の利点は、品切れの心配が少なく、配送日程も余裕をもって行える点が挙げられれます。
近年の、早めのお中元のほか「お中元離れ」の傾向もあるようです。
お中元離れ:変化する日本の贈答文化

近年、日本の伝統的な贈答文化である「お中元」が衰退しつつある現象、いわゆる「お中元離れ」が話題になっています。
かつては、目上の人や取引先に感謝の気持ちを込めて贈る習慣として広く定着していましたが、現代のライフスタイルの変化や価値観の変容によって、その慣習が薄れつつあります。
本記事では、お中元離れの背景や要因、そして今後の日本の贈答文化の在り方について考察します。
そもそも、お中元は中国の道教由来の行事で、旧暦の7月15日に祖先を供養する「中元節」から発展しました。日本では江戸時代に定着し、商家を中心に取引先やお世話になった人への感謝を示す贈り物として広まりました。
企業間の付き合いや個人間の親交の証として、長年にわたり日本社会に根付いてきた文化です。
しかし、時代が進むにつれ、お中元の形態は変化していきました。昭和後期には、デパートや百貨店でお中元商戦が繰り広げられ、大規模な商業イベントとして発展しました。その後、バブル崩壊や経済の停滞を背景に、お中元の意義が徐々に見直されるようになりました。
お中元離れが進む理由として考えられる点が↓
- ライフスタイルの変化
現代では、家族構成の変化や個人主義の進展により、義務的な贈答文化が減少しています。かつてのように親族や職場の関係者に大量のお中元を贈ることが一般的ではなくなり、シンプルな人間関係を望む人が増えています。 - 経済的負担の軽減
お中元の習慣には一定の経済的負担が伴います。特にビジネスシーンでは取引先への贈答品の費用が企業の経費に影響することもあり、コスト削減の一環としてお中元を廃止する企業が増えています。
- コンプライアンス意識の向上
企業倫理の強化に伴い、お中元を「贈収賄」と見なす風潮も広がっています。公務員や大手企業の社員が過剰な贈答品を受け取ることが問題視されるケースもあり、これが企業間でのお中元離れを促進する要因となっています。 - ギフト市場の変化
近年では、インターネットを活用したカスタムギフトやサブスクリプション型のプレゼントが人気を集めています。従来の形式的なお中元よりも、個別の好みに合わせた贈り物の方が受け入れられやすい傾向があります。
新たな贈答文化の方向性
お中元離れが進む一方で、日本の贈答文化が完全に消滅するわけではありません。新しい形態として、より個人の価値観に寄り添う贈り物や、特定のイベントに応じたギフトが注目されています。
データコム株式会社による【20代~50代の働く世代対象とする夏のギフトに関する調査】によれば、
①お中元やサマーギフトなどを贈らない人が70%超え
②それぞれ35%以上が「贈りたい相手がいない」と回答
③上司に「アルコール」、家族に「アイス」や「ゼリー」を贈る人が多数
④お中元は「相手の好み」、サマーギフトは「夏らしさ」が選ぶポイントお中元とサマーギフトでそれぞれ贈り物を選ぶ際のポイントについて、お中元は「相手の好みに合う」が最多の34.1%、次いで「失礼に当たらない」が21.2%とマナーが重視される贈り物ということもあり、相手を気遣う回答が上位になりました。
一方のサマーギフトは、「相手の好みに合う」27%とほとんど同率で「夏らしさ」が26%となりました。カジュアルに贈れるからこそ、形式にとらわれることなく夏を感じて貰えるギフトを選ぶ人が多いと考えられます。
お中元やサマーギフトなどの贈り物は下火になっているものの、夏の風物詩として手軽に贈れるギフトがあると生活者としては喜ばしいのではないでしょうか。
【調査概要】
調査方法:インターネット調査
地域:全国
調査方法:QIQUMOによるアンケート調査
調査人数:450人
調査時期:2024年6月データコム株式会社 調べ
https://www.datacom.jp/2902/news-release/
これまでの、お中元文化から変化の兆しは明らかに見られつつも、夏の時期の贈り物は姿形を変えながらも「贈る気持ち」は続いている様子もうかがえます。
お中元の形式は時代とともに変化していますが、感謝の気持ちを伝えるという本質は変わっていないようです。

パーソナライズされたギフトとして
近年では、名前入りの商品や相手の趣味に合わせたギフトが人気です。画一的な贈答ではなく、相手にとって価値のあるものを贈る文化が発展しています。
家族(親や子や孫)へ 体験型ギフトの普及
モノではなく体験をプレゼントするスタイルが人気を集めています。旅行券、レストランの食事券、オンラインレッスンなど、特別な体験を贈ることが、新しい贈答の形として定着しつつあります。
サステナビリティを意識した贈答
エコフレンドリーな商品や社会貢献につながるギフトを選ぶ人も増えています。フェアトレード商品や環境配慮型の食品・日用品が、贈り物の選択肢として注目されています。
お中元離れは、時代の変化や価値観の多様化による自然な流れとも言えます。しかし、日本人の「感謝を伝える文化」そのものが消えるわけではなく、形を変えながら進化を続けています。従来の形式的なお中元から脱却し、よりパーソナルで心のこもったギフトが今後の贈答文化の主流となるでしょう。
あなたの周りでは、お中元の習慣がどのように変化していますか?
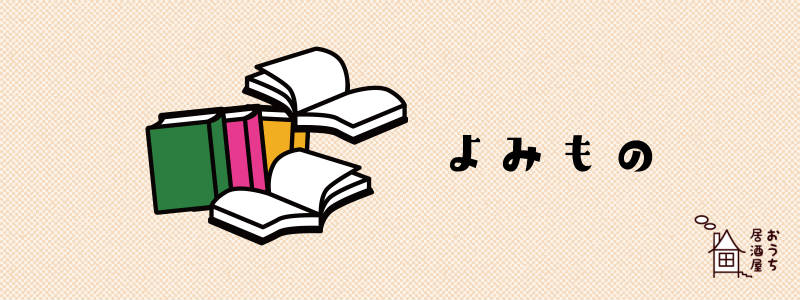
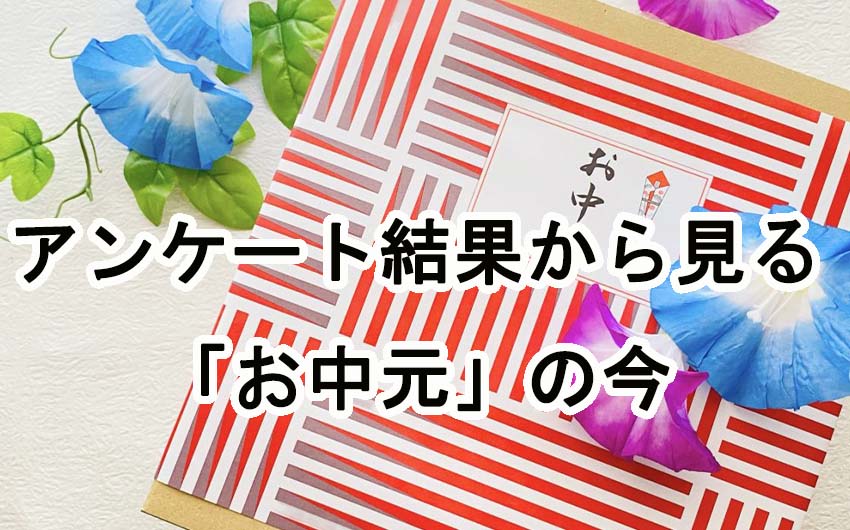


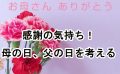
コメント