食のタブーと雅な隠語
日本の食文化には、しばしば雅な言葉で食材を表現する伝統があります。その中でも特に異彩を放つのが、猪肉を「牡丹(ぼたん)」と呼ぶ慣習でしょう。

鮮やかな色彩を持つ花の王、牡丹と、野趣あふれる猪肉。一見すると結びつかないこの二つの言葉がなぜ結びついたのか、そこには日本の長い歴史と独特の食文化が深く関係しています。
この興味深い隠語のルーツを探り、それが日本の食に与えた影響について考察します。
仏教の伝来と肉食の禁止
猪肉が「牡丹」と呼ばれるようになった背景には、仏教の日本への伝来と、それに伴う肉食の禁止という歴史的経緯が深く関わっています。
仏教が日本に伝来したのは6世紀半ばのことです。当初は個人の信仰として広まりましたが、奈良時代には国家的な保護を受けるようになり、その教えは社会全体に大きな影響を与えるようになりました。仏教の基本的な教えの一つに「不殺生戒(ふせっしょうかい)」があります。これは、生き物の命を奪うことを禁じる戒律であり、これには肉食も含まれていました。
天武天皇四年(675年)には、「肉食禁止令」が発布されます。これは、仏教の教えに基づき、牛、馬、犬、猿、鶏などの家畜の肉を食べることや、それらの肉を市場で販売することを禁じるものでした。この禁止令は、以後も度々発せられ、平安時代にはほぼ定着し、日本の支配層や都市住民の間では肉食が忌避される風潮が強まりました。
しかし、完全に肉食が絶たれたわけではありませんでした。狩猟を生業とする人々や、肉を薬として利用する習慣は、民衆の間で細々と続けられていました。特に、山野で捕獲される鳥獣、つまり「野鳥」や「野生動物」については、家畜とは異なる扱いを受けることがありました。
隠語としての肉:「けだもの」から「花」へ
肉食が禁止された時代、人々は肉食の習慣を完全に捨てることはできませんでした。
そこで生まれたのが、食材としての肉を指すための「隠語」です。
これは、禁忌を犯す行為を直接的に表現することを避け、遠回しに、あるいは比喩的に表現することで、社会的な目を欺き、自らの欲求を満たそうとする人々の知恵が生み出した文化現象と言えます。
なぜ「獣」を意味する言葉ではなく、「花」や「植物」など、自然界の美しいものに例えられたのでしょうか。
そこには、肉食に対する罪悪感を和らげる、あるいは禁忌の対象を雅なものに転じることで、精神的な抵抗感を減らすという心理的な側面があったと考えられます。
また、食材としての肉を、直接的な表現を避けて暗示することで、周囲に悟られずに売買・消費するという目的もありました。
この隠語は、単なる言葉遊びではありませんでした。
それは、肉食という行為が、公には認められないものの、水面下では脈々と続いていたことを示す証拠でもあります。特に、一般の民衆や特定の職に就く人々(例えば狩人や猟師)にとっては、貴重なタンパク源であり、生活を維持するために不可欠なものでした。
猪肉はなぜ「牡丹」なのか?
数ある肉の隠語の中で、猪肉が「牡丹」と呼ばれるようになった理由には、大きく分けて二つの説があります。
1. 盛り付けの見た目から

最も有力かつ広く知られているのが、「盛り付けの見た目」に由来するという説です。猪肉は、その色合いが牛肉や豚肉に比べて赤みが強く、また、薄切りにして皿に並べると、その重なりが華やかな牡丹の花びらのように見えることから、「牡丹」と呼ばれるようになったと言われています。
特に「牡丹鍋」のように、味噌仕立ての鍋に薄切りの猪肉が並べられる様子は、まさに鍋の中に大輪の牡丹が咲いたかのような美しさです。
この視覚的な類似性は、人々が禁忌の肉を、いかにして美しく、そして罪悪感を伴わずに享受しようとしたかの表れでもあります。
食欲と美意識、そして社会的な規範との間で揺れ動く人々の心が、この雅な隠語を生み出したと言えるでしょう。
花札(かるた)の絵柄から

もう一つの説は、花札(かるた)の絵柄に由来するというものです。
花札には、毎月の代表的な花が描かれており、7月の札には「萩に猪」、そして10月の札には「紅葉に鹿」、11月の札には「柳に燕」が描かれています。しかし、特定の時期の猪を直接「牡丹」と結びつける花札の絵柄はありません。
この説は、むしろ「花札の絵柄に描かれた動物たち(猪、鹿など)の肉を、その絵柄に描かれた植物(萩、紅葉など)の名前で呼ぶようになった」という、より広範な隠語の形成過程と結びついています。つまり、猪肉の「牡丹」だけでなく、鹿肉の「紅葉(もみじ)」、鴨肉の「桜(さくら)」といった他の隠語も、同様の背景を持つということです。
この説は、花札が庶民の間で広く親しまれ、日常生活に浸透していたことを示唆しています。絵柄を通じて、間接的に肉を指し示すことで、公然と肉食について語ることを避けつつも、仲間内では共通の認識を持つことができたのでしょう。
他の肉の隠語とその由来
猪肉の「牡丹」以外にも、肉食禁止の時代に生まれた雅な隠語はいくつか存在します。
鹿肉:紅葉(もみじ)
こちらも、皿に盛り付けた鹿肉の色合いが紅葉した木の葉のように見えることから、あるいは花札の「紅葉に鹿」の絵柄に由来すると言われています。鹿肉は猪肉と同様に赤みが強く、美しい盛り付けが映える食材です。
馬肉:桜(さくら)
馬肉が「桜」と呼ばれるのは、その肉の色が鮮やかな桜色をしていることに由来すると言われています。特に、新鮮な馬刺しは美しいピンク色をしており、桜の花びらを連想させます。また、春先に桜の咲く季節に馬肉を食べるのが流行したという説や、桜の咲く時期に食欲が旺盛になることから、馬を食べる習慣があったという説もあります。
鶏肉:柏(かしわ)
鶏肉が「柏」と呼ばれるのは、柏の葉の形が鶏の羽に似ているから、あるいは柏の葉が茶色く変色してもなかなか落ちないことから、鶏の丈夫さや生命力に重ね合わせたという説があります。また、柏餅のように神聖な意味合いを持つ植物に例えることで、肉食の罪悪感を軽減しようとしたのかもしれません。
これらの隠語は、それぞれが食材の持つ特徴や、当時の文化、人々の心理を反映しています。肉食が禁止され、しかし食欲は抑えられないという状況の中で、人々がどのようにして禁忌と向き合い、独自の食文化を育んできたのかを示す、非常に興味深い事例と言えるでしょう。
文化的・社会的影響:隠された食文化の形成
肉食の隠語は、単に言葉の遊びに留まらず、当時の日本の社会と文化に大きな影響を与えました。
隠された肉食の伝統
肉食禁止令は、表向きは厳格に守られているかのように見えましたが、実際には、隠語を用いることで密かに肉食が続けられていました。特に、猟師や山間部の住民にとっては、肉は貴重な栄養源であり、彼らの生活には欠かせないものでした。これらの隠語は、そうした「隠された食文化」を維持するための重要なツールとして機能しました。
また、一部では病気治療のための「薬食い」として肉を摂取することが黙認されるケースもありました。この「薬食い」という概念もまた、肉食のタブーを回避するための、ある種の「隠語」であったと言えるでしょう。
食材の再評価と現代への影響
明治時代に入り、日本が近代国家を目指す中で、肉食禁止令は廃止されます。文明開化の波とともに、西洋の食文化が流入し、肉食は奨励されるようになります。しかし、長きにわたる肉食のタブーは、人々の意識の中に深く根付いていました。一気に肉食が普及したわけではなく、徐々に受け入れられていきました。
現代において、「牡丹鍋」や「桜鍋」といった言葉は、単なる隠語としての意味合いを超え、特定の食材を用いた伝統的な料理名として定着しています。これらの料理は、その名の通り、盛り付けの美しさや、食材の持つ独特の風味を楽しむものとして、現代の食卓でも愛され続けています。
例えば、「牡丹鍋」は、猪肉の風味豊かな旨味と、味噌のコクが絶妙に調和した冬の味覚として、今なお多くの人々に親しまれています。また、観光地などでは、その土地ならではのジビエ料理として、猪肉や鹿肉が提供され、地域の食文化の特色を彩っています。
これらの隠語は、単に過去の遺物ではありません。それは、日本の食文化が、厳しい制約の中でいかにして創造性を発揮し、独自の進化を遂げてきたかを示す生きた証拠であり、現代の私たちに、食の多様性と奥深さを教えてくれています。
言葉に宿る食の物語
猪肉が「牡丹」と呼ばれる慣習は、単なる言葉の不思議ではありません。
そこには、仏教の教え、国家の政策、そしてそれらの中で生きる人々の知恵と工夫が織りなす、壮大な食の物語が隠されています。肉食が禁じられた時代に、人々は隠語を用いることでタブーを回避し、食の喜びを追求しました。特に猪肉の「牡丹」は、その視覚的な美しさと、秘められた食の欲求とが結びついた、まさに雅な表現と言えるでしょう。
現代において肉食はごく当たり前のものとなりましたが、「牡丹鍋」といった言葉は、かつての隠された食文化の記憶を今に伝えています。
これらの隠語を知ることで、私たちは日本の食文化の多層性、そして言葉が持つ豊かな意味合いを再認識することができます。次に猪肉を口にする機会があれば、ぜひ「牡丹」という呼び名に込められた、日本の奥深い歴史と人々の知恵に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。それはきっと、食の体験をより豊かにしてくれることでしょう。
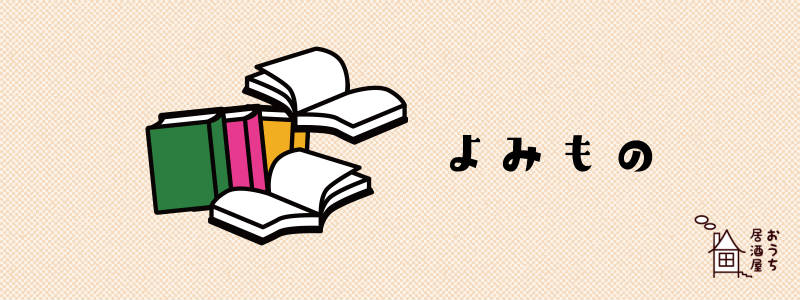



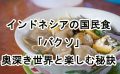
コメント