
日本は、豊かな自然に恵まれている一方で、梅雨時期の大雨や夏の台風といった自然災害に見舞われやすい国土でもあります。
近年、気候変動の影響もあり、これらの災害は激甚化・頻発化する傾向にあり、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。
大雨や台風は、河川の氾濫、土砂災害、浸水、停電、交通網の寸断など、様々な被害をもたらします。
これらの災害が発生した際、私たちの安全を確保し、生活を維持するためには、事前の備えが不可欠。
この記事では、梅雨時期の大雨や夏の台風に備えて、日頃から準備しておくべき常備食、避難バッグの中身、そして災害に対する心構えについて、詳しく解説していきます。
なぜ今、備えが必要なのか
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、災害はいつ起こるかわかりません。
過去の災害事例を振り返ると、事前の備えが不十分であったために、避難が遅れたり、生活に必要な物資が不足したりするケースが少なくありません。
特に、近年頻発する集中豪雨は、短時間で甚大な被害をもたらすことがあり、避難の判断が遅れると、命に関わる事態に発展する可能性もあります。
また、台風も、勢力を保ったまま上陸することが増え、広範囲にわたる停電や交通網の遮断を引き起こすことがあります。
このような状況を踏まえ、私たちは「自分自身と家族の命を守る」「被災後の生活を少しでも安定させる」という意識を持ち、日頃から災害に備えておく必要があるのです。
梅雨と台風:それぞれの特性と注意点
梅雨と台風は、どちらも大雨をもたらす自然現象ですが、その特性や注意すべき点が異なります。
 梅雨
梅雨
時期: 6月から7月にかけて、日本列島に停滞する梅雨前線によって、長期間にわたって雨が降り続く期間です。
特性: 広範囲にわたって比較的穏やかな雨が降り続くことが多いですが、梅雨末期には局地的に激しい雨(ゲリラ豪雨)が発生することもあります。
注意点: 長期間の降雨による地盤の緩み、河川の水位上昇、低い土地での浸水、土砂災害の発生に注意が必要です。また、湿度が高くなるため、食中毒や感染症の予防も重要になります。
 台風
台風
時期: 夏から秋にかけて(特に7月から9月)、太平洋上で発生する熱帯低気圧が発達したものです。
特性: 強風と大雨を伴い、勢力が強い場合は暴風となることもあります。進路や速度が予測しにくく、広範囲にわたって大きな被害をもたらす可能性があります。
注意点: 強風による家屋の倒壊や飛来物、高潮による浸水、河川の氾濫、土砂災害、停電、交通網の寸断などに警戒が必要です。
これらの特性を踏まえ、それぞれの季節に合わせた備えをしておくことが重要です。
いざという時のために:常備食の準備

災害発生時、電気や水道、ガスなどのライフラインが途絶える可能性があります。
また、物流が滞り、食料品や生活必需品が手に入りにくくなることも考えられます。
そのため、日頃から非常時に備えた常備食を準備しておくことが非常に重要です。
常備食を選ぶ際のポイント
長期保存が可能: 賞味期限が長く、常温で保存できるものを選びましょう。レトルト食品、缶詰、ドライフーズなどが適しています。
調理不要または簡便な調理: 電気やガスが使えない状況を想定し、そのまま食べられるものや、水やお湯を注ぐだけで食べられるものを選びましょう。
栄養バランス: 炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂取できるよう、様々な種類の食品を組み合わせましょう。
アレルギー対応: 家族にアレルギーを持つ人がいる場合は、アレルギー対応の食品も用意しておきましょう。
ローリングストック: 消費期限の近いものから順に消費し、その都度新しいものを買い足す「ローリングストック」という方法を取り入れると、常に一定量の食料を確保できます。
具体的な常備食の例
主食:
アルファ米(乾燥米):水やお湯を注ぐだけでご飯になります。
レトルトご飯・餅:温めるだけで食べられます。
乾麺(うどん、そうめん、パスタ):水とカセットコンロがあれば調理可能です。
パンの缶詰:長期保存が可能で、そのまま食べられます。
シリアル、クラッカー:調理不要で、手軽にエネルギー補給ができます。
おかず:
缶詰(魚、肉、野菜、果物):長期保存が可能で、栄養も豊富です。
レトルト食品(カレー、シチュー、丼もの):温めるだけで手軽に食べられます。
乾燥野菜、フリーズドライ食品:水やお湯で戻して使えます。
高タンパク食品(プロテインバー、ジャーキー):手軽にタンパク質を補給できます。
その他:
飲料水:1人1日3リットルを目安に、最低3日分は用意しましょう。
保存水:長期保存が可能な水です。
スポーツドリンク:水分とミネラルを同時に補給できます。
粉ミルク、離乳食:乳幼児がいる家庭は必ず用意しましょう。
栄養補助食品(ビタミン剤、サプリメント):必要に応じて用意しましょう。
調味料(塩、砂糖、醤油など):少量でも用意しておくと便利です。
缶切り、栓抜き:缶詰を開ける際に必要です。
カセットコンロ、ガスボンベ:調理が必要な場合に備えて用意しましょう。
ラップ、アルミホイル:食品の保存や調理に役立ちます。
ウェットティッシュ、キッチンペーパー:衛生管理に役立ちます。
ゴミ袋:汚物やゴミの処理に必要です。
備蓄量の目安
最低3日分: 電気や水道などのライフラインが途絶えた場合、自力で生活できる最低限の期間です。
できれば1週間分: 支援物資が届くまでには時間がかかる場合もあるため、1週間分の備蓄があるとより安心です。
定期的に備蓄品の賞味期限を確認し、期限切れのものは入れ替えるようにしましょう。
身を守るために:避難バッグの準備
災害が発生し、避難が必要になった場合に備えて、すぐに持ち出せる「避難バッグ」を準備しておくことが重要です。
避難バッグは、両手が空くリュックサックタイプがおすすめです。
避難バッグに入れるべきもの
非常食:
水(500ml程度のペットボトル数本)
レトルトご飯、パンの缶詰など、調理不要で食べられるもの
チョコレート、カロリーメイトなど、高カロリーで手軽にエネルギー補給できるもの
貴重品:
現金(小銭も含む)
健康保険証のコピー
運転免許証、マイナンバーカードのコピー
預金通帳、キャッシュカードのコピー
印鑑
連絡先リスト(家族、親戚、友人、職場などの電話番号やメールアドレス)
地図(避難経路などを書き込んだもの)
救急用品:
救急絆創膏、ガーゼ、包帯
消毒液
痛み止め、解熱剤、常備薬
マスク
ウェットティッシュ
体温計
救急セット(綿棒、ハサミ、ピンセットなど)
生活用品:
スマートフォン、携帯電話の充電器、モバイルバッテリー
ラジオ(手回し充電式が望ましい)
ライト(懐中電灯、ヘッドライトなど)と予備の電池
軍手
レインコート、ポンチョ
下着、着替え(季節に合わせたもの)
タオル、ティッシュペーパー
生理用品、おむつ(必要な場合)
ポリ袋(ゴミ袋、防水対策など多用途)
サランラップ
防寒具(ブランケット、アルミシートなど)
ホイッスル(助けを求める際に)
カッターナイフ、ハサミ
ロープ(丈夫なもの)
ガムテープ
油性ペン(連絡事項などを書き込む際に)
その他:
ヘルメット、防災頭巾
眼鏡、コンタクトレンズと保存液(必要な場合)
筆記用具、メモ帳
子どもや高齢者、障がいのある方がいる場合は、それぞれの必要に応じたもの(お薬、ミルク、介護用品など)
避難バッグの保管場所と定期的な見直し
避難バッグは、非常時にすぐに持ち出せるよう、玄関や寝室など、分かりやすい場所に保管しましょう。また、年に1回程度、中身を確認し、食料品や電池の期限切れ、衣類のサイズの変化などをチェックし、必要に応じて入れ替えを行いましょう。
災害発生時の行動と心構え
常備食や避難バッグの準備と並んで重要なのが、災害発生時の適切な行動と心構えです。
情報収集
テレビ、ラジオ、インターネットなどで、気象庁や自治体からの最新の情報を常に確認しましょう。
避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急))に注意し、適切なタイミングで避難行動を取りましょう。
周囲の人と協力し、情報を共有することも大切です。
避難行動
自宅が安全な場合は、無理に避難する必要はありません。ただし、少しでも危険を感じたら、早めに安全な場所へ避難しましょう。
避難場所は、自治体が指定する避難所だけでなく、安全な親戚や知人宅なども検討しましょう。
避難経路を確認し、複数のルートを想定しておきましょう。
避難する際は、非常持ち出し袋を必ず持参し、徒歩での移動を基本としましょう。
避難中も、周囲の状況に注意し、安全を確保しながら行動しましょう。
在宅避難
自宅が比較的安全な場合は、在宅避難という選択肢もあります。
在宅避難をする場合でも、停電や断水に備え、非常食や水、生活用品などを十分に確保しておきましょう。
スマートフォンやラジオなどで情報収集を行い、必要に応じて支援を求めましょう。
近隣住民と協力し、安否確認などを行いましょう。
心構え
冷静に行動する: 災害時はパニックになりやすいですが、冷静さを保ち、状況に応じた適切な行動を心がけましょう。
助け合いの精神: 周囲の人と協力し、助け合いの精神を持つことが大切です。特に、高齢者や障がいのある方など、支援が必要な人には積極的に声をかけましょう。
デマに惑わされない: 不確かな情報やデマに惑わされず、公的な機関からの正確な情報を確認しましょう。
自助・共助・公助の意識: 自分の身は自分で守る「自助」、地域の人々が協力し合う「共助」、国や自治体による支援「公助」のそれぞれの役割を理解し、連携していくことが重要です。
地域との連携:共助の重要性
災害発生時、行政の支援がすぐに届かない場合もあります。そのような状況においては、地域住民同士の協力、いわゆる「共助」が非常に重要になります。
自治会・町内会への参加: 地域で行われる防災訓練や情報共有の場に積極的に参加し、顔の見える関係を築いておきましょう。
防災ボランティアへの参加: 地域の防災活動に積極的に参加し、災害時の支援体制づくりに貢献しましょう。
近隣住民との連携: 日頃から近隣住民とコミュニケーションを取り、災害時の協力体制について話し合っておきましょう。安否確認の方法や、支援が必要な人の情報を共有しておくことも大切です。
日頃の備えが未来を守る
梅雨時期の大雨や夏の台風は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。しかし、日頃からの備えをしっかりと行っておくことで、被害を最小限に抑え、安全を確保することができます。
この記事で解説した常備食や避難バッグの準備は、あくまでも基本的なものです。ご自身の家族構成や住んでいる地域の特性に合わせて、必要なものを準備し、定期的に見直しを行うようにしましょう。
そして、何よりも大切なのは、災害に対する意識を高め、いざという時に冷静かつ適切に行動できる心構えを持つことです。
「備えあれば憂いなし」という言葉を胸に、私たち一人ひとりが防災意識を高め、安全な暮らしを守るための行動を実践していきましょう。未来の自分と大切な家族のために、今できることから始めてみませんか。
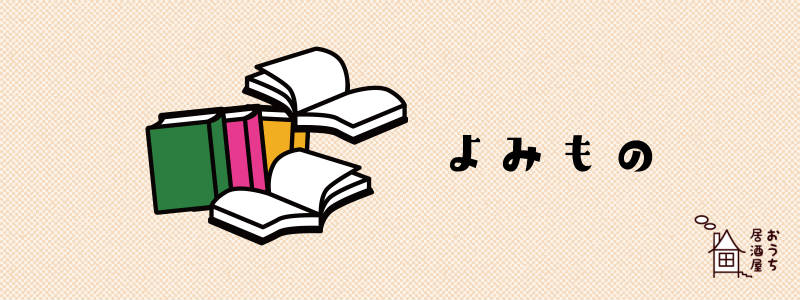
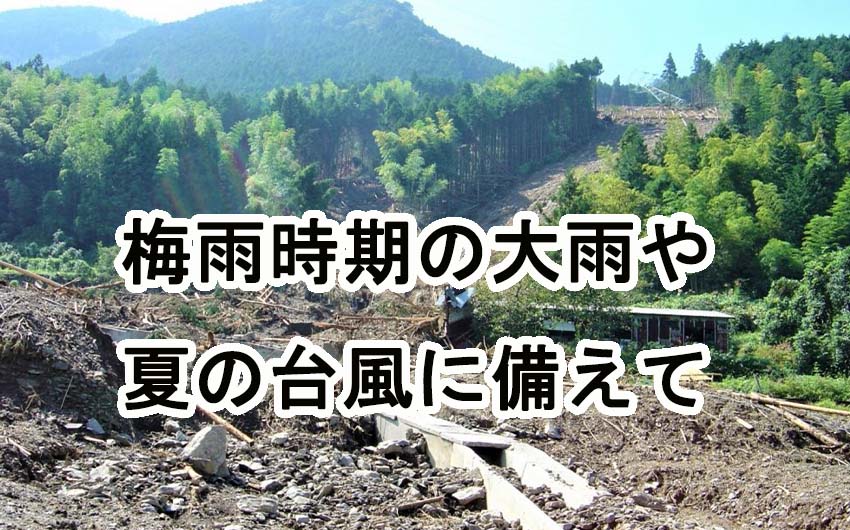



コメント