クリスマスに食べる料理として焼き鳥は一般的に取り扱われていませんが、鶏肉を使った料理はクリスマスの定番として知られています。
- ローストチキン
- フライドチキン
鶏肉を使ったクリスマスメニューは、多くのクリスマスメニュー中でも人気の高いものではないでしょうか?

ではなぜ、日本でのクリスマスにはチキンが食べられるようになったのでしょうか?
そもそもクリスマスを祝う理由は?
現在、私達が暮らすここ日本では、クリスマスと言うと、大切な人とプレゼントを交換したり、クリスマスディナーやケーキを楽しんたり、一種のイベントとなったクリスマス。
みなさんも御存知のとおり、本来のクリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う日です。正しくは、イエス・キリストの降誕を記念する日。
キリスト降誕祭
聖誕祭
クリスマス = Christmass
これは、Christ(キリスト)とMass(ミサ)が合わさってできた言葉だとされています。
日本でのクリスマスはいつ頃からお祝いするようになったのでしょうか?
日本のクリスマスの発祥は、1552年(天文21年)に山口県でイエズス会の宣教師であるフランシスコ・ザビエルがキリストの降誕祭のミサを行ったことが最初と言われています。
室町時代の周防国・長門国を収める大内氏、当時の当主である大内義隆が、宣教師フランシスコ・ザビエルの布教を受け入れる形で、日本でクリスマスを祝う、キリスト降誕祭が行われます。
日本初のクリスマスは山口県で行われた!
歴史
室町時代、守護として山口を中心に治めていた大内氏は、京都をはじめ朝鮮半島や中国大陸から様々な文化、学問、宗教を取り入れ、西国一といわれるほどの経済的発展とともに文化あふれる個性的なまちづくりを行いました。
第31代当主大内義隆は、フランシスコ=サビエルの布教の願いを寛容な心で受入れ、翌1552年旧暦12月9日(西暦12月24日)、山口の地で降誕祭が行われました。これが日本で初めてクリスマスが祝われた日と記録されています。史料 松田毅一・川崎桃太訳『フロイス日本史』中央公論社 村上直次郎訳注『続異国叢書 耶蘇会士日本通信(豊後篇)』上・下、一九三六年、帝国教育会出版部
山口市は、2006年にスペインのナバラ州から「クリスマス発祥の地」として認定されています。毎年12月には「12月、山口市はクリスマス市になる。」を合言葉に、イルミネーションやコンサート、グルメなどさまざまなクリスマスイベントが開催されています。?
クリスマスが日本に定着したのは明治時代以降で、1900年ごろにクリスマスに関連する商品が販売されるようになりました。不二家の創業者である藤井林右衛門が1910年にクリスマスケーキを販売したことで、日本でもクリスマスというイベントが認知されていきました。
クリスマスにチキンを食べるようになった経緯

クリスマスに七面鳥を食べる習慣は、1860年代のアメリカで先住民のインディアンがヨーロッパから来た移民に七面鳥をプレゼントしたことに由来しています。
ヨーロッパからアメリカへの移民たちが食糧難で冬を越せないと困っていたところ、先住民のインディアンから、七面鳥をはじめたくさんの食材をプレゼントしてもらったことで、飢えをしのぐことができました。
移民たちは飢えをしのぐことができたことに感謝し、七面鳥をローストして振る舞うようになったと言われています。
そこから、感謝祭として現在でもクリスマスなど大勢の人が集まる行事で七面鳥のローストが食べられるようになりました。
実はイギリスではローストビーフ、北欧では肉より魚、スウェーデンでは豚肉料理など、世界各国ではクリスマス=チキン(鶏肉)というわけもないのは、七面鳥をローストして食べる文化はアメリカで興った習慣であることから。
日本では、明治時代以降にアメリカからクリスマスの文化が根付くのですが、七面鳥は入手しにくいことからチキンをローストして食べるようになりました。
また、1970年代に大手フライドチキンチェーンが「クリスマスにはフライドチキン」というキャンペーンを行ったことがきっかけとも言われています。あ
る外国人が「日本には七面鳥がないので、ケンタッキーフライドチキンでクリスマスを祝う」と言って来店したことがきっかけという説が有力です。ここもアメリカナイズされたクリスマスの習慣が根付いているということでしょう。
今年のクリスマスは焼き鳥にしましょう
あまりにも、アメリカンなクリスマスの習慣。
とすれば、少し日本的に「感謝祭」として、日本食でもある「焼き鳥」を楽しんでみるのはいかがでしょう。

臘八のあとにかしましくりすます(明治25年)
1892(明治25)年 正岡子規(25歳当時)
明治の頃には、季語として「クリスマス」が取り入れられていますね。
日本ではじめて俳句に詠まれたであろうクリスマス。
その後も、正岡子規は
八人の子どもむつましクリスマス(明治29年)
贈り物の数を尽くしてクリスマス(明治32年)
4年後、さらにその3年後にクリスマスを季語とした句を詠んでいます。
最初は、やかましく感じていたクリスマスを、年月を経て次第に、幸せな風景として感じ、それを詠んだ句に変化が分かります。
これに象徴されるように日本文化に浸透し、親しまれるようになった感が伝わってきます。
今年も、メリー・クリスマスであふれる日本であると良いですね。
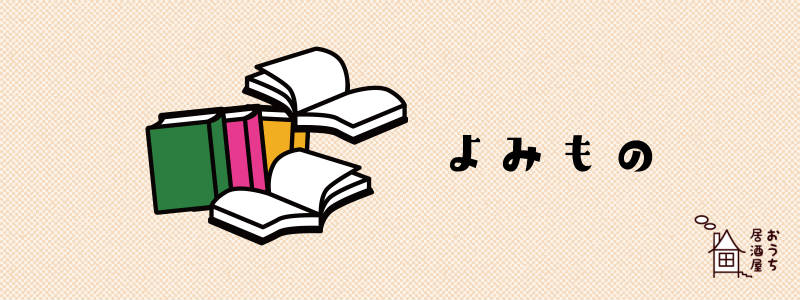

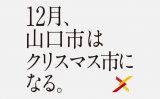



コメント