2025年、今年も桜が楽しみな季節になりました。

日本各地の桜の開花日が同じ地点を結んだ線のことを、桜前線と呼びますが、お住いのエリアの桜は、今年はいつ頃満開でしょうか?
今年は、いつもより早い?遅い?
日本人ならではの春を楽しみにするワクワク感が嬉しい季節ですね。
桜は、日本を象徴する花、樹木とよく言われますが、なぜでしょう?
桜は日本を象徴するなぜでしょうか?
ひとつに、南北に長い国土の日本列島、気候的な特徴として四季があり、その季節ごとの変化、その変化を象徴的に捉えたものとして、春は桜の開花、夏は蝉の鳴き声、秋は紅葉、冬は・・・と、春の到来を象徴するのが「桜」とされていいて、古くは奈良時代、万葉集にも詠われています。
平安時代には、桜を愛でる文化が生まれ、和歌にも詠まれるようにもなります。
現在、よく目にする桜といえば「ソメイヨシノ(染井吉野)」、ソメイヨシノは江戸時代に誕生した桜の品種で、これが全国に広まったとされます。
庶民も、身分を問わず花見が広く楽しまれるようになります。
浮世絵や、歌舞伎、能といった日本の伝統芸術にも、桜は多く描かれていきます。
春の訪れを告げる花であり、春、人生の門出を祝うかのように咲き乱れる桜の美しさに、多くの日本人が心惹かれたのだと思います。
桜といえばお花見、お花見といえば・・・
奈良時代から平安時代に貴族の楽しみのように始まったとされる「花見」。
もともと、花鳥風月を詠む風習があった上流階級の人々は、梅や桜、季節を感じる花草、生き物を眺める、愉しみがありました。
一方で、米作の田んぼには「田の神様」がいると考えられてきた人々の生活の中で、桜が咲くと、供え物をしたり、その年の豊作を願い、桜の咲く時期や具合を見ながら、その年の豊作具合を占ったり、桜の下で行う宴を楽しんでいたそうです。
引用:お花見の始まり
お花見の始まりは、古くは平安時代の貴族が桜を見ながら歌を詠んだり、蹴鞠(けまり)をした行事が始まりで、次第に農民の間でその年の豊作を願って桜の下で宴会をするようになったといいます。 庶民がお花見を楽しむようになったのは江戸時代の寛文年間のころからです。 当時は寺社の境内に咲く桜の観賞でした。

桜を愛でながら食べる、お花見弁当にはじまり、お花見だんご、桜もち。
春の旬の食材を使った色とりどりなおかずとデザートが入った花見弁当
赤(ピンク)は、春の息吹桜を表し、白は桃の節句に飲むお酒、白酒を表し冬の名残を、夏の予兆、緑を表現している桜もち
桜もちは、食紅でピンク色に染めた生地であんを包み、塩漬けの桜の葉を巻いた関東風と、道明寺粉で作った生地であんを包み、塩漬けの桜の葉を巻いた関西風があります。

いずれも、桜を愛でながら、家族や親しい人たちと桜を楽しむために発展してきた、お花見グルメ。
現代のお花見グルメと言えば
現在、お花見の食べ物、その定番といえば、桜もちや三色団子以外に、ピクニック的に花見を楽しむ場合の、巻きずしやおにぎり、サンドイッチと片手で手軽に食べることが出来るものが主流です。

お花見で、お酒を飲んだり、本格的に食事をするとなると、旬の色とりどりの食材を使ったお花見弁当や、ちらし寿司、唐揚げや卵焼き、ピザや焼き鳥といった人気のメニューが有るようです。
お花見の名所とされる場所には、その時期になると出店が並んだり、といった光景もよく目にします。
お花見での食事を楽しむ時には、場所に応じて、田の花見客や鑑賞者への配慮も必要です。公園など公共の場所での飲酒や、もくもく煙や匂いを出してしまう焼肉などは敬遠される場合もあります。
花見場所に応じて、その場所に適したメニューをチョイスすることも、花見を楽しむ大きなポイントになりますね。

おうちのお庭に咲く桜を楽しむ場合には、串にさした焼き鳥がおすすめ!
片手で食べられ、手も汚れにくく、温かくても冷めても美味しい!
家族、おじいちゃん、おばあちゃん、お子さんも老若男女問わず愛される焼鳥は、みんなで楽しめるメニューと言えるでしょう!

今年のお花見は焼き鳥にチャレンジしてみませんか?
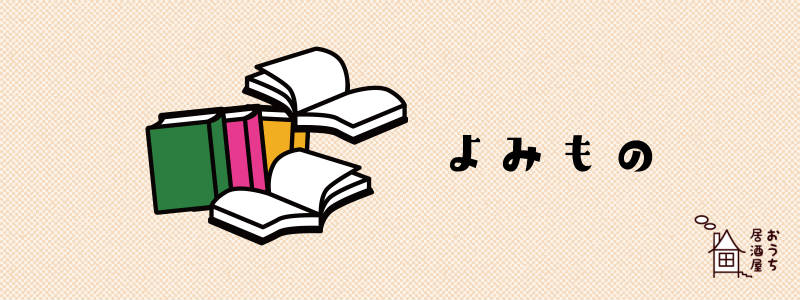
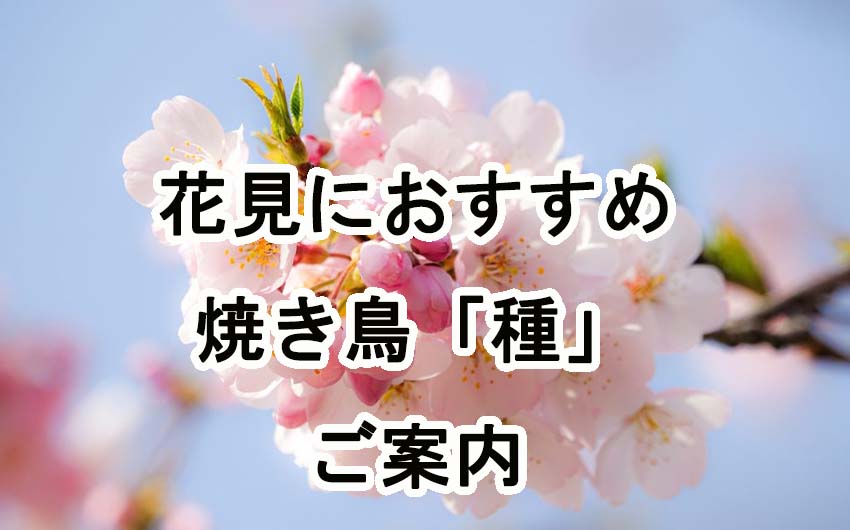








コメント