女の子の成長と幸せを願うのが「上巳(じょうし)の節句」、桃の節句やひな祭りとも呼ばれるが、毎年3月3日。
そして、5月5日は「端午の節句」。
男の子の誕生を祝い、健やかな成長を祈る、日本古来の行事です。
上巳の節句(3月3日)の祝い方

桃の花や、雛人形を飾って菱餅や草餅、ちらし寿司、ひなあられといったものを行事食とします。
平安時代、子どもたちの遊びで「ひいな遊び」といって、雛人形を使って人形に衣服を着せたり、調度を整えたり飾ったりする遊び?、それがひな祭りの起源とされています。
上巳の節句は、中国から遣隋使によって同時期の平安時代に伝わったといわれています。伝わった上巳の節句では、水で身を清めるという「上巳の祓い」という風習があり、「ひいな遊ぶ」と混ざって、雛人形を川に流す「流し雛」が生まれたことで、3月3日の上巳の節句と、ひな祭りが混ざりあったような風習として受け継がれたとされています。
女の子の節句として定着するのは、江戸時代に幕府が制定した「五節句」のひとつとして、女の子の健康と幸福を願う行事が行われていたことから。
桃の節句とも呼ばれ、桃の花が咲き始める時期、その桃の花は厄を払う象徴ともされ、雛人形は女の子が遊ぶ遊びであったため、女の子が主役の節句という位置づけ。

白酒を飲み、菱餅やちらし寿司でお祝いをし、もちろん白酒はアルコールを含むため、代わりに、子どもには白酒に似た、アルコールを含まない甘酒を用いたそうです。
ちなみに、甘酒はその栄養価の高さから、江戸時代ごろ夏の栄養補給として人気を得て広まったことから、俳句の夏の季語としても知られています。
端午の節句(5月5日)の祝い方

端午とは?
旧暦における「午の月」は5月に当たります。
十二支でみると
0 申 猿
1 酉 鶏
2 戌 犬(狗)
3 亥 豚(猪)
4 子 鼠
5 丑 牛
6 寅 虎
7 卯 兎
8 辰 龍
9 巳 蛇
10 午 馬
11 未 羊
5月、最初の「午の日」、つまり5月5日を5節句のひとつ「端午の節句」とした。
節句とは、年中行事を行う節目に当たる日のことを指し、5節句とは
人日(じんじつ) 1月7日 七草の節句
上巳(じょうし) 3月3日 桃の節句・雛祭
端午(たんご) 5月5日 菖蒲の節句
七夕(しちせき) 7月7日 笹の節句・七夕
重陽(ちょうよう) 9月9日 菊の節句
これら5つの節目の行事を指します。
端午節句は、菖蒲の節句とも呼ばれ、男の子の節句として、柏餅を食べ、五月人形や鯉のぼりを飾り、菖蒲湯に浸かったりしますね。

柏餅の他、日本各地で違いがあり、笹や竹の葉が邪気を払う力を持つとされ、それに包まれた「ちまき」を食べて災から身を守るとした地域もあります。
鹿児島県では「あくまき」と呼ばれる餅菓子を食べる風習があります。
鹿児島県 あくまき
「あくまき」は、主に端午の節句で食べられる鹿児島県独特の餅菓子で、“ちまき”と呼ぶこともある。関ヶ原の戦いの際、薩摩の島津義弘が日持ちのする食糧として持参したのがはじまりだという説がある。保存性が高いことと、その腹持ちの良さから、薩摩にとって長く戦陣食として活用され、かの西郷隆盛も西南戦争で食べていたといわれる。こうした背景から、男子が強くたくましく育つようにという願いを込めて、端午の節句に食べられるようになったといわれている。
「あくまき」は、もち米を木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸した後、そのもち米を孟宗竹(もうそうちく)の皮で包んで、灰汁水で数時間煮込んでつくられる。灰汁に含まれるアルカリ性物質がもち米の繊維を柔らかくするとともに、雑菌の繁殖を抑え、長期保存ができるようになる。高温多湿で食糧が腐敗しやすい鹿児島県において、まさに先人の知恵がつまった料理である。
鹿児島では、4月の中頃にもなれば県内のスーパーや商店で、あくまきが並び始め、家庭で作る人用に、もち米、灰汁、孟宗竹の皮など、あくまきの材料も日常的に販売されるのを見かけます。

「あくまき」は、主に端午の節句、こどもの日で食べられる懐かしい食べ物として、鹿児島県独特の食文化です。
アルカリ性食品で、ちまきと呼ぶこともあり、関ヶ原の戦いの際、薩摩の島津義弘が日持ちのする食糧、陣中食、戦闘食、兵糧食、携帯食、縁起物として持参したのがはじまりだという説があります。
昔は、鹿児島のどこの家庭でもおばあちゃんやお母さんが腕を振るって作ったそうです。
ぷるんとした滑らかな食感で、あくまきそのものに、あまり味はなく、きなこや砂糖、黒蜜やはちみつをかけて食べるのが一般的だそうです。
砂糖醤油や、醤油だけで食べるというふうに、様々な楽しみ方も有る様子。

山形県や、福島(会津)では、「つの巻き」として「ゆべし(柚子やくるみなどを用いた餅菓子)」を笹で巻いた郷土菓子が端午の節句に食べられます。

ちなみに、ゆずを使ったゆべしは熊本県や岡山県などの郷土料理として
また、くるみを使った醤油風味のゆべしは、福島、仙台、山形、長野などの郷土料理です。
全国各地で、少しずつ形状や、素材、味、製法は違えど、様々な「ゆべし」が存在しているのは興味深いですね。
あくまきや、ゆべし、懐かしいふるさとの味です。
日本各地、節句にまつわる行事食や祝菓子、その由来や意味を再確認するのは、なかなか楽しいかもしれません。
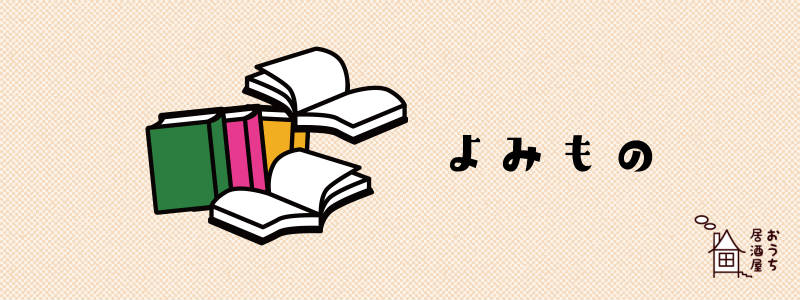

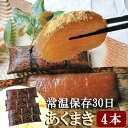


コメント